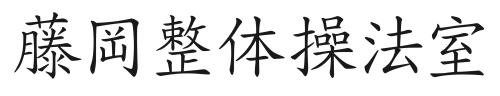整体通信 令和7年10月号より〜図はリアルで入手してね
季節の体
朝夕涼しくなって、9月27日から急な腰痛が増えてきています。井本整体(人体力学)独自の語句が出てきますので、裏面の図を参考にしながら読み進めてください。
先月号にて、冷えとわからぬ冷えが体に影響するということを書きました。また冷えと乾きが一連のものであることも記しておきました。乾きが最も多く見られるのが今からの時季で、乾くと粘膜が過敏になるということも過去の整体通信で書いてあります。水分の吸収を促すには熱めの汁物が良いことも、過去にしつこいほど書いているので、既にご承知の方も多いことと思います。
そこで、今回は少し違う視点の話をいたします。風呂に入ってすぐ寝床に直行しないことや、寝床の敷物の方が重要であることなどは、これまでの記述や話から復習してください。
日本の暑い夏では湿気の多い熱い空気によって肺の中が刺激されて、蒸れと高温に反発するべく筋反射によって肺の脈管が緊張し、その反応によって神経を介して胸椎三四五番の可動性が悪くなり、内部の筋肉の緊張の波及によって上胸部三角点に緊張が現れるようになります。この状態が続くと硬くなってきます。こうなると胸郭の伸び縮みが制限されるため、息を詰めた状態に近くなります。暑いところで仕事をする人は特に夏の間中こういう疲れやすい状態で、それでも冷房を使うなどしてなんとか休めながら気を張って乗り切るのです。
さて、今年は8月27日から体(環境)が変わり始めたと先月号に書きましたが、人の体は季節の変わり目を先取って変化を始め、それがおよそ一ヶ月前、鈍い人で二週間前や寸前(変化しないほど鈍い人もいる)、早い人で一月半前から体に現れてきます。私はそれだけでなく季節の変化の兆しそのものも禁じ取って意識に上らせているわけですが、ほとんどの人は無自覚、無意識に変化が起こります。ですので私が当時「一気に冷えてくるよ」と言っても、ハイと返事はするものの別にどうとも受け止めなかった様子ですが、実は無意識に語りかけているのです。
こうしてこわばっていた肺の働きが徐々に緩んできて、今時分に体が楽になればそれで良いのです。
肺の働きは上胸部三角点の弾力と肩甲骨の位置や可動性だけでも大雑把に読み取れます。この部分は腸骨の可動性と連動します。また後頭骨とも連動します。図に示した腸骨稜と仙骨を結んだ三角のエリアに特に状況が現れやすいのです。
つまり、夏の暑さで上胸部三角点が硬直するだけでなく、それに伴って腰の周り、とりわけ腸骨、仙骨の周辺にも緊張が継続していくのです。頭部もそうです。
それゆえ涼しくなってホッとなったときに上胸部三角点の息抜きと共に首や頭部、腸骨周りも連動して緩んでくれば良いのです。
ところが気温が下がって汗をかく量が減ると、それまで処理していた老廃物の始末を小便に回す必要が出てきて腎臓の仕事が増えます。間に合わない時は一旦胃酸に回すため胃酸過多になってみたり食欲が増してみたりしますが、まだ初期の今頃はそこまでではないかもしれません。なにせ先ずは左、古くなると右というふうに仕事を回してゆきますので、最初は胸椎十十一十二の左側が腎臓の反射で張ってきます。これがだんだん硬くなってくると、体の正常な反りが失われて、ちょうど図の黒丸のあたりから前屈気味になります。こうなると連動が上手くいかなくなります。同じようにこの力が上に行くと首が張ったり頭が
痛くなったりするわけです。常日頃から首がこわばる人は、その緊張は内部の血管に伝わり、常に血管がこわばると硬くなり、動脈硬化となってゆきます。
涼しくなって呼吸器がホッと楽になって上胸部は緩むのに、連動が邪魔されて腸骨周りが緩まないとき、その強弱の差を腰痛として感じるわけです。人によっては症状が上に出たり、腰は緩むのに胸部が緩まず不整脈が出たりというふうに、人によって様々な現れ方をします。このようなとき、どこかの緩みを伝えるのを邪魔しているものがあるならば、そこをちょっと刺激して働きを助けると、極端な事例では腰を触らずして腰痛を解消させることに成功するなんてことも起こりうるわけです。