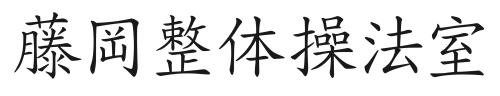整体通信 令和7年1月号より 食い過ぎですよワッハッハ
季節の体
まだまだ寒い日が続きますが、春の到来は少しばかり早くなりそうです。というのも、春先の変動が体に表れた事例が、12月23日と30日、年明けて元日にわずかに観られたからです。(1月1日現在)
12月23日の春めきの時には、外をうろついていたどこかの猫も一時間程度、春先の特徴が現れていました。早い人で1月10日前後から観られ始めるというのが、標準的な推移です。つまり、三週間ほど早いということになります。
生命は環境の変化を、実現より早めに察知する能力が備わっています。そして事前に準備を進めてゆき、その経過に閊えがあれば、少しばかりの変動を起こすことで、備わった体力を賦活させます。こうして季節がすっかり変わる頃には、体も余裕を持って適応できるようになっているのです。
その人の感受性によって、早くて一ヶ月前に感じ取ります。一般的なのが二週間前です。鈍い人だと事後となって、慌てて変化について行こうとして、一度体を壊して再び作り直すことで変化に対応しようとします。大風邪はそういった、生きる働きによって起こすものです。世間では悪いものとして捉えられがちですが、体の為すべきことを済ませば、自然と収束してリフレッシュするものなのです。くしゃみと鼻水だけで経過が完了する風邪と、熱がだらだらと続いて治ったんだかどうだかわからない状態がひと月もふた月も続く風邪との違いは、体の感受性と弾力の状態によるものです。
春先に順応する際に体に生じる変化がどこかで閊えることによって、起きる変動というのが決まってきます。代表的な変動には次のようなものがあります。
粘膜の過敏:これには乾きも関係します。水や汁物が足りてない場合もあります。
血管の緊張:年月を経ていると硬化ということもあります。
大雑把に言えば、代表例はこの二つです。もちろんこれだけではありませんが、これに端を発することが多いので、的を射るためにまとめました。
では何が起こるのかというと、頭痛、空咳、喉の不調、くしゃみ鼻水、軽微な花粉症様症状、目の充血、かすみ目、頻脈、動悸、血管の詰まり、痔、生殖機能関連の乱れなどです。
腰椎四番が緩み始めるのはそのあとです。昔は下から上へと緩みが進みましたが、近頃はいきなり頭がおかしくなる人もいますので、昔より今の方が、体を読むことの正確さ、視野の広さ、情報にとらわれない柔軟な感性がより多く必要です。井本整体整体操法の伝統を守るには、根本原則を踏まえた上で常に変わらねばなりません。更に近年は発熱を抑制する薬の影響で、起きるべき変化が起きなくなってしまった若者もいます。春なのに腰椎四番が緩んでこないという、行く末が心配になるような事例も稀に観られるようになりました。若いのに年寄り、いや、年寄りでも緩む人が多いのに、これでは老人以下だと話しても、他人事のように可笑しげに笑うのだから堪りません。その人の場合は脚に急処を見つけて変化させたのですが、不調が治ると来なくなるのが、体力のなさを如実に示しています。こうしたものは季節を三巡はしないと、保つ状態へ自力で持って行けるだけの力は養えないのです。
なお、皮下脂肪を落とす下痢をするのはもっと暖かい日が増えてきてからです。今起こる下痢のほとんどが太ももを冷やしたものであり、別物ですから、下痢をしたと言って喜ぶのはまだ早いです。冷やして起こす下痢も利用価値はありますが、冷えて心臓にショックがいった下痢は気をつけないといけません。
何事も情報に惑わされての自己判断に陥らず、正確に体の声を聴けるように、呼吸法などを生活に取り入れて錬磨するのが、最も楽で間違いも少ないのです。
肩や首が張る
先の記事を読んで、春だから肩首が張って頭が痛むのだなと思った方に、悲しいお知らせがあります。それはおそらく過食からのものです。正月前後は日常的な食習慣からかけ離れた飲食をする機会が多くなる人が多いと思います。過度の飲食は背中の真ん中あたりを後ろへ突き出すような体型になります。背骨の両脇の筋肉も硬く張って盛り上がっていることでしょう。胃袋が広がった成果です。
ちょうどこのあたりには肩甲骨と後頭部に繋がっている大きな筋肉の末端がくっついています。つまり、自らの力で肩首を下に思いっきり引っ張っている状態が続くということです。当然生きた体は反発して引っ張り返そうとしますから、綱引きがずっと続いた状態のまま頭も首も肩も休まらないということになり、その筋肉の緊張を神経がモニターした情報が脳に送られ、まだここが働いているから寝ない方が良いんじゃないですかと注進するものだから、眠りも浅くなり、首が硬いと大事な脳に血液が通りにくく、しかも起きておかねば(緊張に端を発する誤情報なのだが)となると、脳にもっと血液をと心臓が気合いを入れてくれて、頸部の血圧が上がるということになります。因みに腕力に頼って体全体を上手に連動できないパワー型の人だと、そうした緊張や硬直が残っている部位が前腕や胸と肩甲骨の外側となり、指先に血液を送ろうとして血圧が上がることになりますので、薬を飲むより肘湯を日課にする方がより良い対処となります。
さて、過食による肩首頭の不調や高血圧は、胃袋を縮めるだけで良いのです。硬く萎縮させるのではなく、適切に伸び縮みできる弾力を養うには、空腹と満腹のメリハリを付ければ良く、時間や雰囲気と欲求(体の要求ではない欲)に流されないだけで良いのです。
更に良くないことに、こうしたエネルギーの過剰状態を解消しようとして、体の要求、この場合は生きるための破壊の要求が誘発されると、風邪に入ることが多いのです。有り余るエネルギーが消費されるまで、風邪の状態が続くので、熱を引っ込めると長引きます。発熱には力が必要です。先月号でも後頭部の蒸しタオル法を紹介しましたが、38℃程度でもたつくならば、発熱中枢を刺激することで一気に上げてやるほうが、経過も早くてあとが楽です。敏感な体の人は小さい破壊をこまめにおこなっていますので、風邪に入ったというのもわかるし、カーッと熱が上がってベトつく汗が出て、一気に脈が遅くなって平熱以下に下がったのがわかります。その間刺激(光音振動食事などなど)の影響を受けないようにゆったりして、サッと平熱に戻る、いや、戻ろうとしてきたときにはサッと動くことができ、気分も体もリフレッシュしています。嘘ではなく、その間15分ということもあります。このようなときには、まとめて大きな風邪をひくこともありません。蒸しタオルをおこなうときは、4~6時間おきに三セットずつおこないます。次におこなう時間の時、熱が上がりきったり、下がり始めているときにはおこないません。
子供の場合、風邪の要求がある体の時は、はしゃいだり、食欲が普段以上で異様ということが多く、これはエネルギー分散の要求ですから、食べるのを止めさせたりせず、うるさいと言ってムキになって感情的になったりせずに、静かに注意を集めていれば良いのです。分散のあとの虚の時期。即ち平熱以下の時にその成果が現れて、平熱に戻るまでの経過も円滑におこなわれることでしょう。