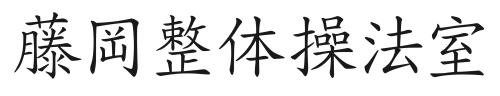整体通信令和7年9月号より〜膝治っちゃった←死ぬやつじゃなかった(笑)
季節の体
既にお気づきのように、朝夕は涼しさを増しています。まだ蒸し暑く感じるものの、総じて観ると一日の気温差が大きくなってきています。8月27日からそれが顕著に感じられます。
寝ている間は無防備で、刺激の変化に対して虚になっていて影響を受けやすくなります。
感覚の閾値(いきち)というのがあります。ここでは生体が敏感に感じ分けられる幅だとお考えください。例えば暑さに慣れた体は暑い温度帯の細かな変化は感じ分けられますが、その範囲からかけ離れた寒さに対しては鈍くなっていて、ひんやりするかなと思うだけです。刺激は受け取っているはずなのに麻痺したような状態になっているのです。敏感に感じわけることが可能な範囲が一人一人にあり、その境目の数値のことを閾値とか、しきい値というふうに言います。化学系の人には馴染みのある言葉です。
今の時季ならば、冷えるほど涼しくなっても暑い中で温度が変化したようにしか感じないのです。
寝ている間は刺激に対して無防備なので、無意識でも安心して眠れるようにすることが睡眠の工夫です。感受性は意識以前の問題なのです。
温度の変化を感じず平衡を保つ働きが一歩出遅れるために、冷えが体に影響するのです。就寝前に入浴してから寝るような人は、寝床の中が蒸れたものが朝方冷えるだとか、窓を開けて寝て無防備なまま朝方の気温低下にさらされることのないよう、窓を閉めてエアコンで気温を一定にするなどの工夫が求められる時季です。就寝中の夜風は肺炎の原因になることもありますし、乳幼児はそのまま亡くなってしまうこともありますので、油断は禁物です。床からじわじわ効いてくる底冷えにもそろそろ準備が必要で、毎年くどいようですが、敷き布団をカバーする敷きパッドなどの良品をそろそろ準備してゆくと良いでしょう。
冷えと乾き
空気の飽和水蒸気量は気温に比例します。気温が高いほど含むことができる量が大きいのです。水分の少ない土地では高温乾燥で、ちょうどモンゴルの夏(数十年前の7月上旬に滞在)がそのような感じでした。標高が高いので夜は寒かったです。日本は水が豊富ですので、高温下では水分の蒸発による蒸気が多く、飽和水蒸気量も多い気温であるため、非常に蒸し暑くなります。
日差しが強いと蒸発も激しく、エアロゾル化して乱反射するので、日差しのきつさが増します。ボイル・シャルルの法則のとおり、気体は温まると体積が大きくなりますので、理屈では人体に掛かる圧が増えることにもなります。あくまでも理論上なので実際の気象や対流、成層圏などにどう影響するかは、観測基礎データを持っている機関でないと仮説も証明もできません。が、圧を感じるような氣がしませんか?肺の中に蒸れた熱い空気が押し込まれて、胸郭の硬い人はそれを吐き出す力が足りなくなるのです。
前段にも書きましたが、8月27日から空気が変わってきています。朝露が増したのも飽和水蒸気量の関係です。温度が下がる分湿度も下がります。つまり、体の冷えと乾きは一連のものなのです。
体が乾くと粘膜が過敏になります。熱中症寸前の肺が蒸れた状態の時には余分な水分を出そうとして水洟が止まらなくなりますが、乾いたときは肺の中の水分を保つために水洟(みずばな:粘度の少ない鼻水)が出ます。尚、心臓に負担の掛かっている場合にも水洟が落ちてくることもあります。外から見える現象は同じでも、理由は人それぞれ異なるので、整体的見地からの観察が必要です。現在只今現れている処の変化はどれも似たような状態でも、連動や流れを辿ると元の原因は異なり、そういうのを手指などで読み取り、短時間で少ない処に必要最小限の刺激で働きかけて経過を読むのが整体操法です。
冷えるとしゃっくりが出ることがあります。乾いたときも冷えたときも、現れる観察点乃至急処は同様の変化が観られます。証拠集めにはまだ他に観るところがありますが、要はしゃっくりも水洟も一連のものであり、更には夏場の暑さに抵抗してきた体の変動から影響を受けることも多いということです。
よく現れる症状がありますが、それを書くことは情操に良くないので、操法の際に直接説明します。ここで言えることは、変化を変化と受け止められないような感受性の鈍りが異常の根本であり、そこにも注意が向けば生き続ける限り、心と体を養い続けることができるということです。
膝、あれから
今年の1月に膝を痛めた話を、3月号で紹介しました。それも8月中旬には九割方回復しました。膝がしっかりと伸びずに引っかかっていたのですが、6月頃から動作の全てを点検して、生活の全てで最大限注意を払って、問題点を改善する動作を継続したところ、かつての俊敏な動きが正確さを纏って戻ってきました。長い年月の基礎訓練の積み重ねも役立っていますが、そういう功を積んでない方でも注力と時間さえかければ効果はあると思います。実行して実現するかどうかが本人自身の問題なのはさておき。
この度は膝を何故痛めるかの問題は抜きにして、かなり大雑把に省略した力学的な観点からのみ説明します。本当は不都合な力が掛かるに至る原因の探求の方が大事であることは、既にご承知のとおりです。
膝関節は基本的に正面に向かって前後に曲げ伸ばしする関節です。背骨のように連続した複数の関節を使って捻ったり傾けたりという動きは得意ではありません。つまり不得意な動きによって無理な力が加わるから痛めるのです。
膝関節の隣の関節は股関節と足関節があり、無制限ではないもののいろいろな方向へ動けるようにできています。また股関節からは腰椎という腰の背骨と、腸骨という骨盤の上方部分の前側に向かって大きな筋肉がくっついていて、太ももの筋力にオーバーワークさせないような初動を司る筋肉があります。
従って膝への負担を減らすことは、足首の弾力性と可動性の回復、股関節の弾力性と可動性の回復、腸腰筋(腸骨筋と大腰筋をまとめて言う呼び名)の働きを活かせる体の使い方の修得、膝に負担が掛からない体の使い方の修得、この四つの訓練によって実現します。
一点に力を集める人体力学体操(整体体操)と共に、中心を意識して動く練習としての日常生活の立ち居振る舞い、これらの継続によって比較的早く膝の故障自体は回復します。あとはそうなったに至る生活習慣の見直しが最も重要ですが、これほど簡単な訓練を継続して積み上げることもできない人には、生活習慣を改めることなど到底無理な話で、訓練の質も量も厭わない人には造作もなくできることです。