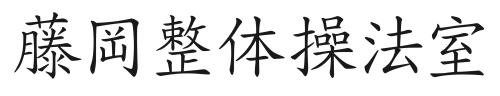整体通信 令和7年7月号より〜保存版だよこれは
季節の体
気温のみでなく湿度も高い日本の夏は、近年凄まじさを増していて、呼吸器の硬直が早い段階で起こるようになりました。
何度も同じことを書いていますが、過去の夏は暑いと言えども30℃越えは珍しく、ほど良き発汗の作用によって、慢性病も夏に好転することが多かったのですが、この25年で大きく様変わりしました。確実なのはもう75年は最低でもこの傾向が続くということくらいです。これは整体的な考えではなく、長期的な天体の運行計算の結果による傾向の経験則で、占いでも予言でも何でもありません。ただの暦の読み方の問題です。結果を知ることができないのが残念ですので、一つの仮説としてホームページ上にもこの原稿を残しておきます。紙媒体にはコピー原紙の保管が過去209号分、さらに外付けのハードディスクにはテキストデータと写真の全てを保管しております。長期的な検証のできる方に見つけてもらえると良いのですが、期待しないで保管のみ徹底しておきます。ホームページは私の死後はプロバイダ解約に伴って閉鎖されるでしょうから、生きているうちの公開手段の一つとして、気休めで掲載いたします。
発汗の作用というのは、蒸散による体温調節と呼吸の補助、盲腸と関連しての重金属の排泄、心理的閊えの排泄、老廃物の排泄などがあり、その際に塩分と水分が同時に排出されます。塩分の中でもナトリウムは筋肉の収縮に関連しますので、部分疲労が深い処の筋肉の、しつこい硬直なども緩むことがあるのです。緩みの格差が大きい場合は緩み残った硬直部位に痛みが出たりするものです。
現在は塩分と水分の過度の排出によって、心臓の筋肉の収縮が阻害されるほどで、疲労困憊から身を守るために、胸や上部胸椎一帯をこわばらせてきます。その力が抜けると持ち堪えられない、つまり息を詰めて耐え続けているのと同じ状態です。そこに高温の湿気を含む空気が入ってきて、その刺激で肺の中が蒸れて、胸郭そのものがこわばって伸び縮みできにくいためにガス交換が上手くいかず、熱い高湿ガスが排泄できなくなり熱中症となるのです。
整体指導において冷やすときは限られていました。やけどの初め~仙骨ショックをするまで、骨折や捻挫の初期~整復をするまで(筋収縮によってぐらつきを軽減するためなので、安定している場合は蒸しタオル法で痛みを軽減する方が良く、整復に来られるまでが長期に及ぶ場合も早い内に蒸しタオル法で持ち堪えないと、骨折などはさっさっとくっついてしまう)、一般人の自己判断ではちょっと微妙な問題なのでここでは記さない事象のだいたい三つでした。そこに肺の中を冷やすという考えが新たにできたのが25年前です。月に二回の当室での勉強会において、過去の記録の紹介をする中で平成12年が初出で、当時私は抵抗なく理解できたものの、一般の人や医療人に肺が蒸れるとか冷房を上手く活用するだとか言うと、理解されないだけでなく嘲笑されることだってあったものでした。この数年来の現在は低ナトリウム血症だとか、水中毒だとか色々周知され始めてきました。
因みに、首や後頭部は熱中症の時でも氷などでキンキンに冷やさないことには変わりありません。首を収縮させると脳への血液が滞りますし、後頭部は生命のコントロールの中枢で、冷やすと体温調節機能が乱れますから、回復が遅れるばかりか脳症などを起こしやすくなります。冷たく乾いた空気を吸うことが回復には最善最速です。冷房の中にいるか、冷蔵庫の冷蔵室か野菜室に鼻先を突っ込む(首を冷やさないように注意)か、車のエアコンの風を吸う(前胸部と首が冷えすぎないよう、また、掃除してないと目に埃が入るので注意)と良いです。塩分と水分は言わずもがなですが、以前山で遭難した話を掲載したように、欠乏時に急に水をがぶ飲みすると、電解質バランスが崩れて目が回り、私の場合は回復に三ヶ月、全快まで三年を要する打ち身状態になりましたので、水の飲み過ぎと飲み方には注意してください。
暑さと蒸れによって、呼吸困難、目が回る、ふらつき、不正出血、皮膚病の悪化、脳血管の弾力異常、心筋や心臓血管の運動異常、目の不調、耳の不調、水洟が止まらなくなる、腰痛、などなど体が緩んでいればあり得ないような問題が賑やかに出てきます。体力を消耗するので過食傾向も現れますが、過食をすると消化不良、肥満による呼吸機能の負担、放熱不良などなども起こるからややこしいものです。
寝ている間に扇風機や冷房の風が直接当たると、筋緊張が持続して筋肉が引きつったり、肺炎になったりしますので、睡眠中は冷房の持続と共に、冷たく乾いた空気を吸えるけれども直接風が当たらない、体も冷えすぎないといった態勢で眠れる工夫を怠らなければ、日中疲労困憊した体の回復に役立つでしょう。あとはナトリウム補給(塩)、カリウム補給(スイカやナスなどの夏野菜)、水分補給(水や麦茶、GREEN DA・KA・RA*糖分過多に注意)、クエン酸も役立ちます。体が必要とする食事を上手に摂れば、過食になることも少なくなります。どうぞ、上手に乗り切ってください。
旧暦の話(続)
前号において明治6年も閏六月(閏水無月)があったと書きました。
実際の季候はどうだったのか調べたところ、以下の文章を見つけました。
抜粋 明治6年(1873年)に日本で発生した異常気象に関する具体的な記録は、資料によって解釈が
異なる場合がありますが、一般的には夏に旱魃(かんばつ)が広範囲で発生し、その後、洪水
や長雨、大雨といった多雨の記録もみられる年として認識されています。
明治6年(1873年)の異常気象の詳細:
旱魃:夏に記録的な旱魃が発生し、各地で水不足や農作物への影響が出ました。
多雨:旱魃の後、洪水や長雨、大雨といった多雨の記録が各地で見られました。
広範囲:これらの現象は、日本各地で観測されており、全国的な現象であったと考えられてい
ます。
明治6年(1873年)には、日本各地で異常気象が発生しました。特に、夏は記録的な猛暑に見
舞われ、冬は豪雪に見舞われるなど、気温の変動が激しい年でした。また、この年は冷害も発
生し、農作物に大きな被害が出ました。
夏:猛暑に見舞われ、各地で記録的な高温を観測しました。
冬:豪雪に見舞われ、特に北日本で多くの積雪を記録しました。
冷害:6月頃に冷害が発生し、農作物に大きな被害が出ました。特に東北地方では深刻な被害
で、餓死者も出たと言われています.
その他:一部地域では大雨や洪水も発生し、被害を拡大させました。
明治6年の異常気象は、当時の社会に大きな影響を与え、特に冷害による食糧不足は深刻な問題
となりました。気象庁によると、異常気象の定義は「ある場所(地域)・ある時期(週、月、
季節)において30年に1回以下で発生する現象」とされています。
明治6年の異常気象は、その後の日本の気候変動や農業政策に影響を与えたと考えられていま
す。